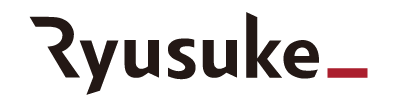パナソニックの凡ミス
大手家電メーカーのパナソニックが新発売するミラーレス一眼カメラの紹介サイトに有料の写真素材が使われていたという問題がニュースになりました。
自社のカメラを紹介する際にそのカメラで撮った写真を使わず、違うカメラで撮った写真を掲載していたようです。
このニュースは一見すれば凡ミスですが、私は別の点が気になりました。
それは、「このカメラの価値は何か?」という、根本的な問いです。
カメラのライバル
ユーザーがミラーレス一眼カメラを買う大きな理由はスマホよりも「いい写真/映像が撮れること」でしょう。ミラーレス一眼カメラの最大のライバルは他社のカメラではなく、スマートフォンです。単に見たものを記録するだけの用途であれば、撮影以外の機能があるスマホのほうが遥かに経済的です。スマホで一眼カメラと同じ品質の撮影できるのならば、わざわざ高価なミラーレス一眼カメラを買う必要はないでしょう。
最近のスマホは10万円程度のミラーレス一眼カメラと同等レベルの写真が撮ることができます。素人目に違いはわかりにくくなっています。必然的にスマホカメラと性能に大差のない安価なデジタルカメラは淘汰されました。
評価軸の変化
写真の良さを決める評価軸は時代とともに変化しています。かつてカメラの良さを決める重要な評価軸は画質(画素数)でした。家庭用の民生機器の画質は悪く、TV放送やポスターに使われるような写真/映像には遠く及びませんでした。
画質は今ではほぼ頭打ちになっています。どのカメラ/スマホでも肉眼で見た光景に近い記録が可能です。その反動か、昭和のカメラを使って写したような少し不明瞭で味のある作品が「エモさ」という価値になっています。
動画撮影についても同様にスマホでTV放送に耐えうる画質の撮影が可能です。差別化要素としては一眼カメラのシネマティックな色表現やスマホにはない背景ボケの描写力が着目されています。
忘れられた顧客
話を戻して、パナソニックのカメラの予定販売価格は20万円を超えています。20万円はプロ仕様のカメラほどの高級価格帯ではありませんが、スマホと比べると高価です。他社と一線を画すような違いがなければカメラ単体に20万円ものお金を出すユーザーは少ないでしょう。
パナソニックの商品説明ページ(Webサイト)ではカメラのカラーバリエーションが大々的に紹介されていましたが、それがライバルと差をつける決定的な要素になるのでしょうか。カラーバリエーションであれば他のメーカーも後追いで簡単に真似できるでしょう。
往々にして開発系のメーカーは細かな仕様や誰も使わない新機能、価格設定、カラー展開などに気を取られて、エンドユーザー目線を見失いがちです。
今一度、カメラの本質的な価値に立ち返る必要がありましょう。